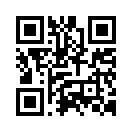。あらためて太平洋を地図で眺めてみると、ニューギニアって経度的にはまったく東京と同じなのですね。ラバウルはその東だから、かつては何でそんな東太平洋まで進出したのかと思っていましたが、ほぼ南下しただけ。当時は南洋諸島は信託統治領でしたので、ちょっとコマを進めただけの感じだったのでしょうか。西太平洋のマレー作戦でジャワまで進出したとしても、豪州から攻撃されれば資源輸送もままならない。そこで米豪分断作戦が必要で、ラバウルからガダルカナルに航空基地を確保する必要があったのだそうです。(なるほど。)真珠湾攻撃も、実行しなかったらミッドウエイー、ウエーキから航空攻撃されるし、アリューシャンからもそれは可能。(だからアッツ、キスカを取ったのですね。)ソ連の航空能力からも本土空襲は可能だったそうです。つまり、本土攻撃を最も恐れた、ということ。いわゆる絶対国防圏の確保です。
対する米側も、欧州戦線が優先ですので太平洋は後回し。開戦となれば香港、フィリピン、マレー、蘭印を取られるのは覚悟していたそうです。欧州では空母は要らないので太平洋に当時2隻。戦艦群は虎の子の部隊を真珠湾で撃沈大破されたので、本当は痛かったのですが、英国東洋艦隊撃沈の事実からも学んで、その後は航空艦隊優先で建造補充されたそうです。珊瑚海やソロモン沖海戦は日本優位。ガ島攻防戦で司令官がゴームリーから強気のハルゼーに替わって潮目が変わったみたいです。つまり、言われてきたように無謀な戦線拡大をしたわけでなく十分戦術的、しかも途中まで互角に戦っていたわけです。
問題は、ルーズベルトに途中講和の意思は全くなかったこと。消耗戦で最後まで戦い抜く決意だったそうです。知米派と言われた山本長官ですが、早期講和を前提にしていたのは生兵法だったということですね。しかし、南方攻撃に南雲艦隊6隻の空母を投入していたとしても、蘭印までの自給圏を維持するにはハワイ、豪州の連合軍に常に苛まれる結果となってじり貧だったでしょう。やはり、ミッドウエー攻略上陸、そしてハワイ占領して初めて安定的な自給圏を確保できたわけです。それしか手がなかったということです。
ここからは私見ですが、唯一の解決策は蒋政権との講和です。そうすれば米国に付け入る隙はなくなってしまう。中国統一と共産党排除を支援する代わりに有為な貿易体制を条件づける、ということで東亜新秩序を日中戦争開始前に打ち立ててればよかったのです。蒋は振武学校卒の帝国陸軍将校経験もあり知日派です。(まあ、周恩来も滞日経験はあるけど。)このくだりは、後日纏めて詳説します。