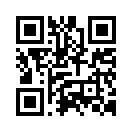このあいだ、高校の仲好し達と中華で飲んだのですが、(ちなみにひとりは、理2から文学部へ転部、哲学で卒論を書いた変人、もうひとりは経済卒で都庁を蹴って公務員試験受け直し国税に入った真面目一筋、最後はWの文学部でバイト中に縁あって広告業界の寵児に、という錚々たるメンバー。)店員に何々ある?って聞いて反応がなかったので、没有?って聞いたら、有って答え。唯一知っている言葉が通じました。(ちなみに、他に知っているのは、日本鬼子くらい。)
そこで、やはり中国語は漢字の発音が想像できて覚えが早いかな?ってことで早速テキストを借りてきました。でも、簡字体なのでさっぱりわからず。仕方なく昔買った漢和辞典で調べて見ると、驚きの略字ばかりです。こりゃ、いかんね。歯が立ちません。でも、日本でも昼や旧の旧字はどうにもイメージがわきません。(子供の頃、オフクロの置き手紙の旧字が読めなくて苦労したのを思い出します。)
というわけで、ちょっと中国語でも勉強して見ようかという気持ちになっています。