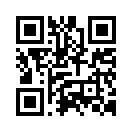読みでがありました。まずは、古代の舟は丸木をくりぬいた丸木舟だったのですって。曲線部の木材の接合ができなかったから。これでも海峡レベルは横断できた。推進はカイによる手漕ぎです。その後の櫓の発明は画期的だったそうです。遣唐使の時代は南シナ海を渡るのは危険でしたが、日宋貿易の頃は季節風も把握してほぼ安全に航海できるようになりました。幕末に洋船がはいるまでは基本的に構造は同じ。上に側板を張って容積を増やしただけの違いです。接合部は草を詰めて密閉。帆は真ん中の柱から、のちの時代にはにずらして張るようになって逆風帆走も可能に。江戸中期にはには千石船まで大きくなります。昼間の風待ち帆走から夜間逆風帆走も可能になって所要日数は大幅短縮されました。でも幕府の海禁政策もあって基本的には和船は内航が中心。河川は重要な交通手段でした。ちなみに川をさかのぼるのは人力による曳舟だそうです。絵で見る和船は川船か沿海船です。そういえば、ちょっと昔までは身の回りに溢れていましたね。ノスタルジックな日本の文化です。