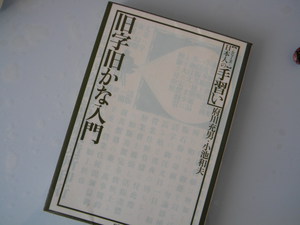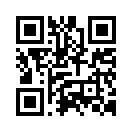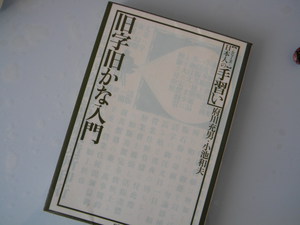
坂本竜馬の彼の姉に宛てた手紙をみると、自由奔放だよね。候文でない昔の書き言葉は、ああなのかなって。平仮名と片仮名が混用され、草書体も色々。我々が習ってきた文字の用法は、明治以来の文字の統一運動の賜物だったのですって。だから我々は昔の書き方に違和感をもつけれど、それがごく普通だったのです。私の姉の嫁ぎ先のお義母さんはサインペンでも素晴らしい字を書いたけれど、草書の使い方も実に優雅でした。「の」は「乃」でなくて「野」を崩した文字。蕎麦屋の「きそば」の「ば」も、何だ、って。飛車角の角の裏の文字は一体何だ?
昔、小学生の頃背伸びして読んだ岩波文庫。その漢字の今と微妙に違うのは単に時代のせい?いや、むしろ昔は様々に使っていたのですって。温の字の日の中の横棒が人だったりして…。高いの高の口は、梯子のような形に書いたり。これは筆使いの手前、書き慣らわした形を活字にしたそうな。随分と自由だね。現代の書きとりでは、×かも。しんにゅうのテンはひとつなの、ふたつなの?どうでもいいのですって。
中国発祥の漢字をずっと使い続けているのは日本だけですって。韓国は国粋運動でハングルに切り替えてしまうし、越南も近代化の過程でアルファベットを導入。当の中国でさえ訳の解らない簡字体に。日本でも維新のときに漢字をやめるどころか、日本語を廃止して英語にしようと主張した人もいたとか。今の漢字とひらがなで本当によかったね。でも、旧の字は旧字の旧の一部、医の字も旧字の医の一部。日本も例外ではないですね。子供の頃のオフクロの手紙、読めなかった。昼の字の旧字。ママの字に似たやつ。私に昼食を用意して自分は出かけた、その昼食の上に置いてあった手紙の意味が解ったのはあとになってからのことでした。